副業・フリーランスが流行っているように、これからは個人で稼ぐことが重要な時代です。
ぼくも来月(2020/10)から脱サラして個人で稼ぐことに専念していきます!
そこで「税金」について学習したことをまとめていきます。
ぼくはこれまでサラリーマンとして生活してきて、恥ずかしながら税金についてあまり考えてきませんでした。。。
サラリーマンの方でも、自分に関することは知っておいた方がよいでしょう!
この記事では税金に関する基本となる、考える上での6つのポイントを説明します。
このポイントを抑えて学習していけば、自分で考えることができるようになり、時代の変化に左右されずに税金について理解することができるようになるでしょう!
また課税対象となるものを大きく3つに分類して説明します。
以下に当てはまる方は学習材料にしてください。
・税金のことをよく知らない
・税金の勉強を始める
・どういう視点で税金について考えたらよいかわからない
・課税対象について大枠を知りたい
難しい単語も一つ一つ簡単に解説していくので、気楽に読めるようになっています。
それでは税金の基礎を学習していきましょう!
税金を考える6つのポイント
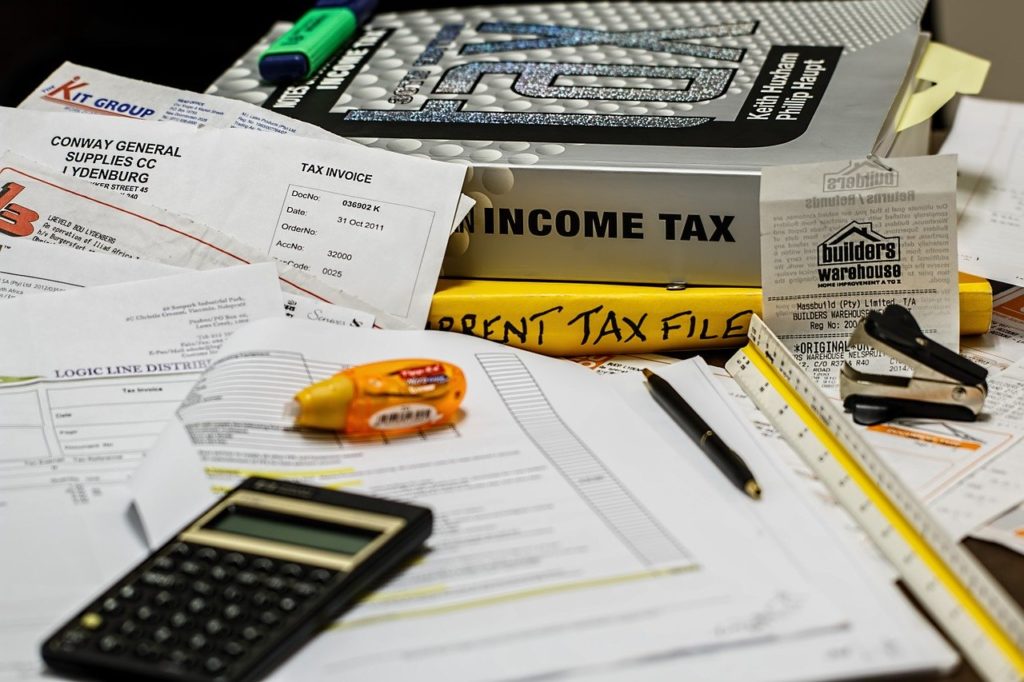
税金は国を運営していくためのお金です。
たとえば以下のようなことで利用されています。
・社会保障
・福祉
・インフラ整備
税金を考える上で大切な6つのポイントを説明していきます。
1)租税法理主義 2)租税公平主義 3)担税力 4)日本の財政事情 5)日本の政策目標 6)執行可能性
すべて大事ですが、我々一般人に重要になってくるのは1)〜3)です。
4)、5)に関しては議員さんが考えることになります。
1)租税法理主義
課税について法律で明確に定められているということです!
当たり前といえば当たり前ですよね。
明確でなければ、いろいろな言い分で納税する人は減るでしょう。
ここで重要なのは法律で定められているということです。
つまりは、法律の改正があれば、税金についての決まりも変更される可能性があるのです。
そして、法律と深く関わっているからこそ、一般人にとって理解が難しくなっています。
2)租税公平主義
公平に課税することです!
公平という考え方には2つあります。
・水平的公平
・垂直的公平
それぞれの考え方を説明します。
水平的公平
同じくらいの経済力がある人には、同じくらいの課税をする、という考え方です。
経済力といっても単純ではなく、人によって多少なりとも差があるのが実情です。
だからこそ税金について学んでおく必要があるのです。
垂直的公平
お金を多く持っている人ほど課税する、という考え方です。
これはなんとなく知っている方も多いのではないでしょうか。
後ほど説明する担税力とも関わってきます。
3)担税力
課税は負担できる範囲内にすることです。
これは重要なポイントといえるでしょう。
多くのお金を扱うほど税金は高くなり、負担の割合を同じにしていくという考え方です。
問題として、頑張って大金を稼ぐ人の方が、課税額が大きくなるため、働く意欲が下がってしまうという点です。
4)日本の財政事情
日本の借金状態を考慮したポイントになります。
前述した通り、税金は国を運営していくための資金です。
日本の借金の状態に合わせて動きが変わってきます。
つまり、法律だけでなく、政策にも大きく関わっているといえます!
5)日本の政策目標
今後、日本をどうしていきたいのか、というポイントになります。
直近でいうと東京オリンピックがこれに当たるでしょう。
追加費用は約6400億円? 五輪延期のカネを日本国民が負担することになる理由
yahooニュース(https://news.yahoo.co.jp/articles/5fe3d28774f63aee1bf144f56a1c91930a61eda0)
6)執行可能性
徴収できる仕組みにしていることです。
いくら明確な法律で、公平な課税制度ができても、税金を徴収できる仕組みがなければ意味ないですよね。
現実的な回収方法を決めておく必要があります。
課税対象になる3つの分類

なにが課税対象でなにが対象でないのか、いろいろなところで述べられています。
でもいっぱいあって、よくわからないですよね。
ぼくはよくわからなかったです。。。
そこで大きく3つに分類して説明します。
まずは基本を理解しておきましょう!
3つの分類は以下になります。
・所得
・消費
・資産
それぞれについて解説していきます。
所得
税金全体の53%が所得から生まれています。
さらに以下の2つに分けることができます。
・法人税
・所得税
法人税は法人の利益に課税されるものです。
一方、所得税は個人の収入に課税されるものです。
どちらも国に納める税金です。
つまり国税です。
簡単にいうと、法人でも個人でもお金を得たら税金を納める必要がある、ということです。
消費
税金全体の32.9%が消費から生まれています。
小学生でも知っている消費税などがこれにあたります。
なにか商品やサービスを購入したときに納税義務が発生します。
資産
税金全体の14.1%が資産を所持していることから生まれています。
資産に関する税金にもいろいろありますが、上位2つは以下になります。
・固定資産税
・相続税、贈与税
固定資産税
これは土地や建物にかかってくる税金です。
地方に納税する地方税となります。
使っていない土地や建物を持っていたら、いつの間にか税金がかかっているので注意しましょう。
相続税、贈与税
名前の通り、相続や贈与にかかる税金になります。
相続や贈与で受けた資産の大きさで金額が変わってきます。
これは国税になります。
巷ではすごく高い印象をもっている方が多いですが、実は全体の2%程度です。
お金持ちの場合、金額が大きくなるので話題になりやすいのだと思います。
【オススメ】年収500万円以上のサラリーマンの税金対策
一般的なサラリーマンでもしっかり対策すれば年間で数十万円の節税できる場合があります。
税金は知らないうちにどんどん上がっています。。。
企業に勤めていても、個人でしっかりと知識をつけておくことが必須です!
税金対策だけでなく、前提となる幅広い知識についてのオンラインセミナーがあるのでこちらより申し込んでみてください。
セミナーの後に個別の相談も可能なので、自分の状況に合わせて対策していくことができます!
まとめ
税金を考える上でのポイントは理解いただけましたでしょうか。
簡単にまとめると、明確に決められており、国民全ての負担の割合を同じにして、的確に徴収するということです。
しかし、完璧に平等に負担を割合を同じにすることができません。
これからも税法は改正されていくことでしょう。
また、課税対象には所得・消費・資産の3つに分類されます。
それぞれについては後日具体的に説明するので少々お待ちください。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました!!!



コメント